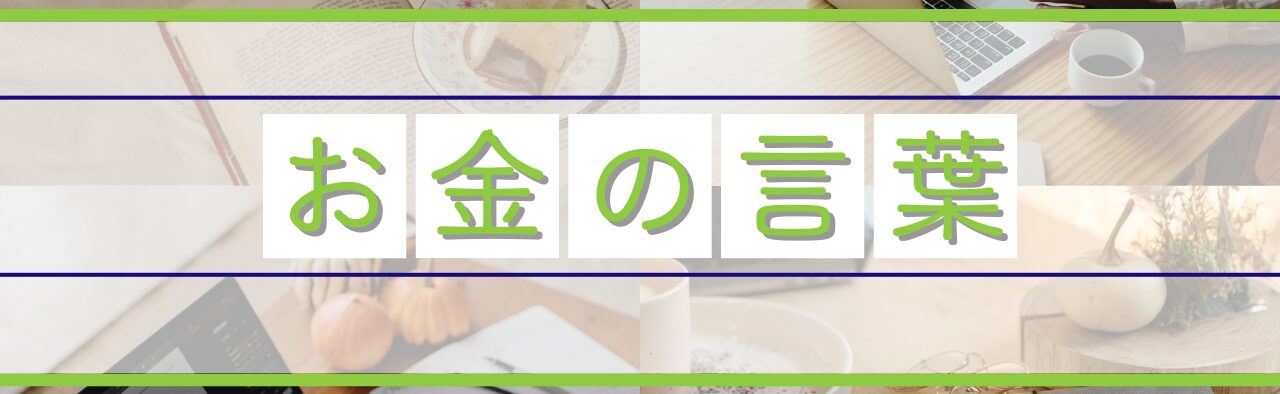【老後のお金シリーズ PART3】
【結論】個人事業主 老後資金対策は、自分専用の制度で準備を
個人事業主 老後資金対策、あなたは考えていますか?
会社員とは違い、個人事業主・フリーランスなら、老後資金も退職金もすべて自分で準備するしかありません。
でも、安心してください。
実は会社員にはない、あなた専用の有利な制度もちゃんと用意されています。
それが、iDeCo(イデコ)です。
たとえば、自営業・フリーランスなら、iDeCoの掛金は月6.8万円まで可能。
会社員(企業年金なし)のiDeCo掛金上限2.3万円/月と比べても、
約3倍もの枠が使えるため、節税効果も資産形成力も高くなるのです。
さらに、もうひとつ。
退職金がない自営業者やフリーランスにとって、退職金づくりの柱となるのが、小規模企業共済です。
これは、会社員より有利な制度ではありませんが、
「自分で退職金を積み立てる唯一の仕組み」として、しっかり活用していきましょう。
【理由】会社員と違い、個人事業主の老後資金対策はすべて自分で
会社員なら、毎月自動的に厚生年金が天引きされ、退職時には会社から退職一時金や企業年金がもらえることもあります。
しかし、個人事業主やフリーランスはそういった仕組みはゼロ。
公的年金は国民年金だけで、将来受け取れる金額は月6万円台と言われています。
しかも、退職金もありません。
そのままでは、引退したときに手元にまとまったお金が残らず、
老後資金が足りなくなるリスクが高いんです。
だからこそ、国が用意してくれている「自営業専用の2大制度」を活用して、会社員に負けない老後資金づくりを目指しましょう。
たとえば、iDeCoと小規模共済の組み合わせは、まさにその王道です。
【具体例】自営業・フリーランスならこの2つ!iDeCoと小規模企業共済を徹底活用
1️⃣ iDeCo(個人型確定拠出年金:第1号被保険者枠)
-
iDeCoは、自分で運用しながら老後資金を準備する制度です。
最大の魅力は、税制優遇がとても大きいこと。たとえば、自営業・フリーランスの場合、
iDeCoの掛金は月6.8万円までOK。
これは、会社員(企業年金なし)のiDeCo掛金上限2.3万円/月と比べても、
約3倍もの枠が設けられているんです。【メリット】
-
掛金全額所得控除 → 大きな節税効果
-
運用益非課税 → 利回りが効率的に育つ
-
自分の好きな運用先を選べる(定期預金型も可)
-
-
【注意点】
-
60歳まで引き出し不可
-
運用リスクあり(元本割れもあり得る)
-
また、iDeCoは受け取り時の**「出口戦略(税金対策)」が少し複雑になります。
このあたりは次回【PART4】で、新NISAとの比較を交えながら、
わかりやすく整理していきますので、楽しみにしていてくださいね。
2️⃣ 小規模企業共済(個人事業主・フリーランスの退職金制度)
次に、小規模企業共済は、個人事業主や小さな会社の経営者が、
自分の将来(廃業・退職時)のためにコツコツ積み立てて、
退職時にまとめて共済金を受け取れる制度です。
さらに、国が運営する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している、安心の仕組みです。
【加入条件】誰でも入れるわけではありません
小規模企業共済は、便利そうだからといって、誰でも入れる制度ではありません。
実は、個人事業主や小さな会社の経営者・役員など、限られた方専用の制度なんです。
なぜなら、この制度は「小規模事業者のための退職金づくり」をサポートする仕組みだからです。
そのため、一定以上の規模になってしまうと、加入資格を失うこともあります。
【対象になる人】
-
個人事業主(フリーランスもOK)
-
会社の経営者、役員
-
家族経営のお店や事務所の方 など
【従業員数の条件】
-
商業・サービス業:常時5人以下
-
製造業・建設業など:常時20人以下
つまり、小さな規模で事業をしている方専用ということですね。
【注意ポイント】
また、法人化(法人成り)しても、役員として条件を満たしていれば、継続して加入も可能です。
しかし、従業員を増やしすぎると、加入資格がなくなることもあるので、
「今はOKだけど、将来的に注意!」という点も覚えておいてください。
-
【特徴】
-
掛金は月1,000円〜70,000円まで、500円単位で設定可能
-
経営状況に応じて増減でき、無理なく続けやすい
-
-
【メリット】
-
掛金は全額所得控除(節税効果抜群)
-
廃業・退職時にまとめて受け取り可能
-
掛金の範囲内で低金利(年0.9〜1.5%)で貸付可能
-
-
【デメリット】
-
廃業・退職などの事由がないと基本的に解約できない(資金ロックあり)
-
途中解約は元本割れのリスク大
-
流動性が低く、ライフプラン変更時の柔軟性がない
-
【公式シミュレーターも便利】
将来もらえる共済金や、どれくらい節税できるか、
気になる方は、公式サイトのシミュレーターで簡単にチェックできます。
👉 小規模企業共済シミュレーター(公式サイト)
(出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構)
【まとめ】まずはiDeCo&小規模共済から
《青太文字:個人事業主 老後資金対策では、iDeCoと小規模共済のダブル活用が王道です。》
これらを活用すれば、会社員にはない掛金枠の大きさや節税効果を活かして、
【太文字】あなた専用の自分年金・自分退職金を育てることができます。
ただし、特にiDeCoは受け取り時の税金対策(出口戦略)が少し複雑で、誤ると余計な税金を払うことになる可能性もあります。
このあたり、資金ロックのない新NISAとの違いを含めて、次回【PART4】でわかりやすく整理します。
ぜひ、そちらもチェックして、あなたに合った老後資金づくりの選び方を身につけましょう😊
【あわせて読みたい】
会社員の老後資金制度も気になるあなたは、こちらもチェック!
👉 サラリーマンの老後資金は大丈夫?退職一時金・企業年金・企業型DCをやさしく整理(PART2)